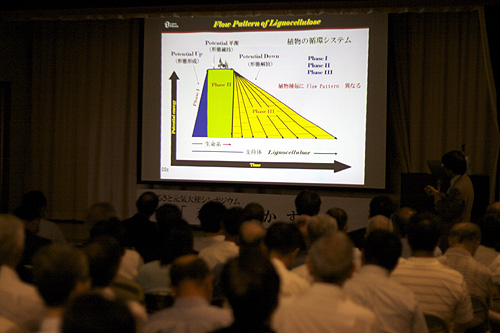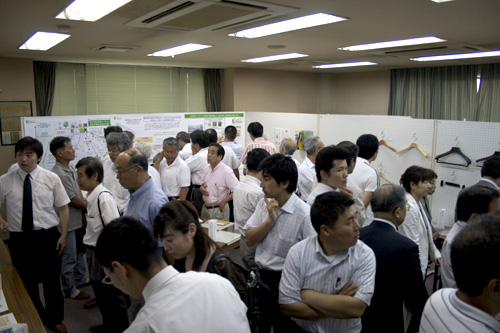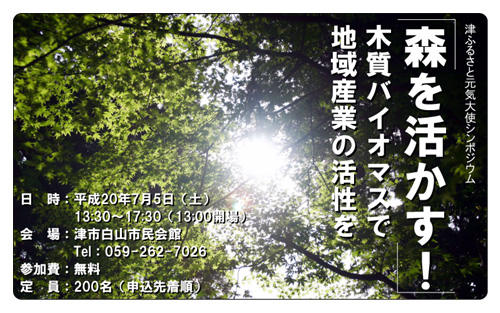当日の様子を写真とコメントでお送りします。

NHK津放送局・萩原キャスターの元気な一声からオープニングスタート。

「こんにちは、三重県の津市からやってきました。」と、松田直久市長。

津ふるさと元気大使、勅使川原郁恵さんにインタビュー。ウォーキングにはまったきっかけは?

NHK−BS『街道てくてく旅』がきっかけだそうです。ウォーキングには多くの出会いがあるそうです。

津市の伝統芸能と「唐人踊り」です。江戸時代から伝わる、「朝鮮通信使」をまねたおどりです。詳しくはこちら。


躍動感にあふれています。

体が柔らかくないとできないですね。職員2号には無理です(涙)。

オープニングイベント後、「高虎ウォークスタンプラリー」出発。

参加者とふれあう「津ふるさと元気大使」勅使川原さん。

最初のチェックポイントは上野東照宮。徳川家康の遺言により、
家康の魂が末永く鎮まる所を作るために高虎が寛永4(1627)年に自らの敷地内に建てました。

門をくぐると大名から寄進された銅製の灯ろうが並んでいます。
それぞれ葵のご紋がついていますが、一つだけないものがあり、それが高虎公の寄進した灯ろうです。

ウォーキング中も津を熱く語る松田市長。

巫女さんにご説明いただきました。

ふむふむ・・・なるほど。

チェックポイントではスタンプをもらいます。
当日使用したスタンプは津市東京事務所で保管しています。
なかなかの力作ですよ!

上野東照宮の次は第2のチェックポイントへ。
これからは上野動物園内に入ります。

上野動物園に入場。
それにしても、なぜ藤堂高虎公のゆかりの地が動物園?
その答えはもうすぐ明らかに・・・。

2つ目のチェックポイントは藤堂高虎公の墓。
なぜ動物園の中にお墓が?
その答えはもうすぐ明らかに・・・(笑)。
まずはスタンプをもらいます。

休日に大勢の家族が集まる上野動物園。
子どもたちに人気のゾウの向かい側に動物慰霊碑があります。その背後に茂る木々の間に、藤堂家の五輪塔が見え、今もここに高虎公は眠っています。かつてここには藤堂家の下屋敷がありました。寛永寺建立の際、高虎公は自らの屋敷地の一部を寄進しました。
今、お墓のあるところは菩提寺の寒松院(かんしょういん)があったからです。
普段は公開されていません。当日は寒松院さんのご好意により特別に参拝することができました。

戦国時代を生き抜いた高虎も病に倒れ、寛永7(1630)年10月5日、江戸藩邸で75年の生涯を終えました。共に家康を支えた天海は「毅然として、寒風に立ち向かう松の木」になぞらえ「寒松院」という院号を贈りました。高虎のお墓は入り口から5番目。そのほか2代〜10代の藩主の五輪塔があります。参加者からは「こんな立派な五輪塔は見たことがない」と言う声も。

3つ目のチェックポイントは閑々亭(かんかんてい)。
晩年の高虎は二代将軍秀忠、三代将軍家光のよき相談役として仕えました。
東照宮に参拝した秀忠・家光を、寒松院の茶室「閑々亭」でもてなしました。
慶応4(1868)年に消失しましたが、明治11(1874)年に再建され現在に至っています。

スタンプを忘れずに。

「閑々亭」の名前の由来は家光が「武士も風流をたしなむほど世の中が閑(ひま)になったので閑々亭と名づけるがよかろう」と言ったことによるといわれています。
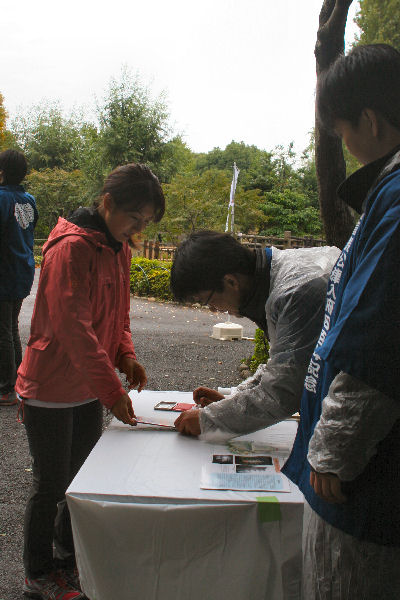
最後のチェックポイントは旧寛永寺五重塔。

寛永寺建立の際、高虎公は自らの屋敷地を進んで寄進しました。
それまでこの地には藤堂家のほかに津軽家、堀家の大名家の屋敷がありました。
寛永寺を建てた甲良宗廣(こうら・むねひろ)は江戸城の建築にも携わっています。ちなみに江戸城の縄張り(設計)は築城の名手、藤堂高虎。現代でいえば高虎が設計者、宗廣は施工者といったところでしょうか。

第2チェックポイントからは東京シティガイド倶楽部の岡部さんと野田さんにご説明いただきました。
動物園は子どもと行くところというイメージがありましたが、こうして歩いてみると、大人も楽しめることがよくわかりました。
また、これだけゆかりの地がある高虎公の偉大さも改めて感じました。